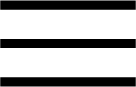健保ニュース
健保ニュース 2025年2月中旬号
中医協が診療報酬改定案を答申
医療DX推進へ体制加算を再編
マイナ保険証利用率の実績要件引き上げ
中央社会保険医療協議会(小塩隆士会長)は1月29日、「医療DXにかかる診療報酬上の評価の取り扱い」等を福岡資麿厚生労働相に答申した。令和6年度診療報酬改定で新設した「医療DX推進体制整備加算」について、7年4月からマイナ保険証の利用率と電子処方箋の導入に応じた6区分の加算に再編。利用率は「45%」、「30%」、「15%」の実績要件を設定し、現行から「15ポイント」、「10ポイント」、「5ポイント」それぞれ引き上げる。医科の加算点数は利用率の高さに応じ「1点」、電子処方箋の導入有無で「2点」の差を設定。10月以降の実績要件は、7月を目途に検討、設定することとした。
福岡資麿厚生労働相は、1月29日の中医協総会に、「医療DXにかかる診療報酬上の評価の取り扱い」について諮問し、同日の会合では、厚労省が提示した個別改定項目にもとづき議論した。
令和6年度診療報酬改定で新設した「医療DX推進体制整備加算」におけるマイナ保険証利用率の実績要件について、6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行したことや、これまでの利用率の実績を踏まえつつ、今後もより多くの医療機関・薬局で医療DX推進のための体制を整備してもらうため、7年4月から9月までにおけるマイナ保険証利用率の実績要件を新たに設定する対応を提案。
合わせて、新たに示された電子処方箋に関する今後の対応などを踏まえつつ、「医療DX推進体制整備加算」の電子処方箋の導入の有無に関する要件を具体化したうえで、導入済の医療機関と未導入の医療機関の間で加算点数に差を設けるとともに、7年3月31日までに多くの導入が見込まれる薬局については電子処方箋の導入を基本とした評価とする対応案を示した。
診療側の長島公之委員(日本医師会常任理事)は、「医療DXの普及を拙速に進めることで医療提供体制に混乱や支障を生じさせてしまった場合、国民の安心や信頼を失い、普及の最大のブレーキとなってしまう」と問題提起した。
マイナ保険証利用率については、マイナンバーカードの保有率が低い小児への配慮を要望。また、電子処方箋の導入状況等を踏まえ、未導入の場合でも「医療DX推進体制整備加算」の現行点数は引き下げるべきではないと訴えた。
そのうえで、「マイナ保険証や電子処方箋について、数字だけを求めて急ぐのではなく、丁寧にきめ細かく環境整備に取り組んでいく必要があることを中医協の総意とすべき」と主張した。
健保連の松本真人理事は、「医療DXの体制整備は補助金で対応することが適当であり、医療機関のランニングコストを診療報酬で手当てする場合でも、患者がそのメリットを実感できることが大前提となる」と言及。
マイナ保険証利用率は、足元で利用が大きく伸びていることを十分に踏まえ、医療機関の努力が促される基準値を設定する必要があるとの考えを示した。
電子処方箋の評価については、「今後は院内処方の機能が追加され、医療機関が電子処方箋を導入する重要性が高まる」と述べたうえで、今夏に新たな目標が提示されることも踏まえつつ、早期の普及を強力に進めるよう要請した。
医療DXの普及を拙速に進めないことを中医協の総意とすべきとする診療側の主張に対しては、「中医協は診療報酬の見直しによる対応を議論する場」と指摘し、理解を求めた。
両側の意見を踏まえ、厚労省が、▽医療DX推進体制整備加算にかかる7年10月以降のマイナ保険証利用率の実績要件の設定にあたっては、マイナ保険証利用率のさらなる向上へ、本年7月頃を目途に、マイナ保険証の利用状況、保険医療機関・薬局における利用促進に関する取り組み状況等、実態を十分に勘案したうえで検討、設定▽電子処方箋は、7年度夏を目途に見直しを行うこととされている電子処方箋に関する新たな目標の達成等に資するよう、その評価の在り方および実効的な措置について、次期診療報酬改定に向けて検討─することを盛り込んだ答申書附帯意見案を作成した。
両側とも附帯意見を承認し、その後、厚労省が「医療DXにかかる診療報酬上の評価の取り扱い」についての答申案を作成。
合わせて、1月15日に福岡厚労相が中央社会保険医療協議会の小塩隆士会長に諮問した「入院時の食費基準額の取り扱い、口腔機能指導加算および歯科技工士連携加算の取り扱いならびに特定薬剤管理指導加算の取り扱い」についての答申案も作成した。
「医療DX推進体制整備加算」は、電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制の有無により、7年4月から現行の3区分を6区分に再編。新設する「加算4・5・6」は、電子処方箋が未導入の医療機関を対象とし、「加算1・2・3」と点数に差を設ける。
7年4~9月のマイナ保険証利用率は、▽加算1・4は45%▽加算2・5は30%▽加算3・6は15%─を基準として設定。「加算3・6」は、6歳未満の患者割合が3割以上の小児科外来診療料を算定する医療機関に配慮し、「12%」へとマイナ保険証利用率の要件を緩和する。
利用率の基準が低い「加算3」は「医科10点、歯科8点、調剤6点」とする一方、利用率の基準が高い「加算1」は「同12点、同11点、同10点」、その間の「加算2」は「同11点、同10点、同8点」と点数に差を設定。
電子処方箋が未導入の医療機関を対象とする「加算4」は「医科10点、歯科9点」、「加算5」は「同9点、同8点」、「加算6」は「同8点、同6点」の新たな点数を設定する。
このほか、「在宅医療DX情報活用加算(医科10点、歯科訪問診療料8点)」について、7年4月から電子処方箋管理サービスに処方情報を登録できる体制を有している「加算1(医科11点、歯科訪問診療料9点)」と、電子処方箋が未導入の「加算2(同9点、同8点)」で点数に差を設けることとした。
7年度政府予算編成の大臣折衝合意を踏まえた診療報酬上の対応である「入院時の食費基準額」は、7年4月1日から1食当たり「20円」引き上げる。
「口腔機能指導加算および歯科技工士連携加算」は、7年4月1日から「歯科衛生実地指導料 口腔機能指導加算」を「2点」引き上げるとともに、「歯科技工士連携加算1(印象採得)」および「歯科技工士連携加算2(同)」を「10点」ずつ引き上げ。
「特定薬剤管理指導加算」は、7年4月1日から「加算3ロ」を「5点」引き上げることとした。
支払側を代表してコメントした松本理事は、答申の内容を了承したうえで、マイナ保険証利用率をさらに高める取り組みを医療現場に期待するとともに、速やかな電子処方箋の導入促進を要望した。
診療側を代表してコメントした長島委員は、答申の内容に異論はないと述べたうえで、「これからも医療DXの推進に取り組んでいくためには様々な環境整備も極めて重要」と強調し、保険者一丸となった協力を求めた。
答申書を受け取った後あいさつした厚労省の鹿沼均保険局長は、「答申にもとづき、速やかに告示や通知の整備を行い、関係者と連携しつつ、円滑な施行に努めていく」と言及したほか、答申書附帯意見を真摯に受け止め対応していく考えを示した。
小塩会長は、医療DXの推進に向けた課題解決への尽力を依頼した。