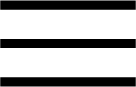健保ニュース
健保ニュース 2025年2月上旬号
健保連・第533回理事会
現役世代の負担軽減が不可欠
宮永会長 改革の実現を強く訴求
健保連は1月27日、第533回理事会を開き、令和7年度事業計画や一般会計予算などを審議し、了承した。冒頭あいさつした宮永俊一会長は、「団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年から高齢化のピークを迎える2040年頃まで、就業人口の急減と高齢者医療費の増加や、それに伴う拠出金負担の急増が見込まれる」と指摘。このような厳しい状況のなか、国民生活の安心の礎である国民皆保険制度を将来世代に繋いでいくためには、「過重な負担を強いられている現役世代の負担軽減が不可欠だ」と強調した。高齢者の窓口負担割合の見直し、世代間の給付と負担のアンバランス解消、負担能力に応じた負担の推進、持続可能な制度に向けた安定財源の確保など、改革の実現を強く訴えていく決意を示した。他方、マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、事業主を通じ4月入社の新規取得者を対象として、マイナ保険証を速やかに取得してもらう取り組みを進めていく考えを表明。マイナ保険証への円滑な完全移行に向け、健保組合と力を合わせて前進していくとした。(宮永会長の発言要旨は次のとおり。)
新年はじめの理事会の開会にあたり、一言あいさつ申し上げる。
昨年、健保組合の皆さんには、事業運営を精力的に進め、本会事業へのご協力をいただいたことを厚くお礼申し上げる。
今年は様々な節目が到来するが、健康保険事業のよりいっそうの発展のため、さらなるご協力を賜るようお願い申し上げる。
昨年1月に発生した能登半島における地震や、9月の記録的な大雨による甚大な被害からの再建、復興がいまだ道半ばということであり、心が痛んでいる。1日も早い復興を願う次第だ。
昨年から今年にかけて、世界の情勢を見渡すと、わが国や主要国において、リーダーの交代や、与野党勢力の逆転、新興勢力の伸長など、従来の政治の枠組みが大きく変わる出来事が続いている。
先週20日には、米国第一主義を掲げる第二次トランプ政権が発足した。
トランプ大統領は、これまでの慣例や常識にとらわれず、独自の政策を進めていくと思われるが、アメリカと同盟国にある日本は、自由と民主主義という同じ価値観を共有するパートナーであり、経済、安全保障の面からも緊密に連携していかなければならない。
インド太平洋地域において、アメリカと他国との橋渡し役を担うなど、国際協調の重要な働きかけをしながら引き続き、良好な関係を日本政府が維持してほしいと思う次第だ。
さて、国内に目を向けると、先週末から始まった通常国会では、来年度の政府予算案や税制改正、予算関連法案などの重要な審議が予定されている。
石破茂首相は年頭の記者会見で、「今後も持続的な経済成長を実現し、生産性向上と賃上げ、消費の好循環の流れを確実なものにしていくためには、社会保障制度の安心の確保は不可欠である」、「少子高齢化等、人口急減が進むわが国において社会保障制度の将来を設計するにあたっては、年齢ではなく負担能力に応じて適切に支え合う全世代型社会保障の構築が必要不可欠である」と述べられている。
いずれも、われわれが従来から主張してきたことであり、現役世代の負担を軽減していくためにも年齢にかかわらず、負担能力に応じて支える仕組みに変えていかなければならない。
少子高齢化がいっそう深刻化する2025年以降においても、日本経済が持続的に成長するためには、企業の投資の拡大と、賃上げのモメンタムを維持するとともに、社会保障制度などのセーフティネットを、時代にあったものに再構築していくことが必要だ。
現段階では、少数与党による大変難しい国会運営が見込まれ、また、夏には参議院議員選挙が控えており、政局がらみの緊迫した状況も予想されるが、難題が山積するなか、国民目線に立った審議が行われることを心から期待している。
昨年末に閣議決定された令和7年度政府予算案においては、高額療養費制度について、自己負担限度額の引き上げや、所得区分の細分化、外来特例を見直すなどの方針が示された。
複数年をかけて、段階的に実施される予定であり、全世代型社会保障構築や保険料負担の軽減につながる内容であることは評価できる。
とは言うものの、現役世代の負担を軽減するという観点では、まだ十分な内容とは言えない。
年収の壁についても、各方面の意見の調整が難しく、とりまとめまでに紆余曲折が予想される。
さらに、8年度に控える子ども・子育て支援金や出産費用の保険適用への対応も課題になる。
今年はまさに「団塊の世代」がすべて後期高齢者となる「2025年」だ。ここから高齢化のピークを迎える2040年頃まで、就業人口の急減と高齢者医療費の増加や、それに伴う拠出金負担が急増していくことが見込まれる。
このような厳しい状況のなかにおいても、国民生活の安心の礎である国民皆保険制度を将来世代に繋いでいくためには、過重な負担を強いられている現役世代の負担軽減が不可欠だ。
健保連は引き続き、高齢者の窓口負担割合の見直し、世代間の給付と負担のアンバランス解消、負担能力に応じた負担の推進、持続可能な制度に向けた安定財源の確保など、改革の実現を強く訴えていく。
さて、新規の保険証の発行がなくなり、1か月が経過した。健保組合の皆さんにおかれては、マイナ保険証への円滑な移行に際し、日頃より協力を賜り、感謝申し上げる。
マイナ保険証は、医療の質の向上と効率化、医療費の適正化に資する、これからの時代に欠かすことのできないツールだ。
マイナ保険証により、今まで分散していた医療・服薬データなどを一元的に見える化できるようになり、より良い医療が受けられるようになる。
限度額適用認定証の手続きが不要となるなど、患者の利便性も向上する。
健保連では、12月の完全移行を前に、普及の方法の1つとして、厚生労働省とも協力して、事業主を通じ4月入社の新規取得者を対象に、マイナ保険証を速やかに取得してもらう取り組みを進めたいと考えている。
事業主と人事担当者、また新規取得者への説明など、健保組合の皆さんのご理解・ご協力を賜ることも多々あるかと思うが、円滑な移行を成し遂げる取り組みとして、何卒よろしくお願い申し上げる。
健保連も、皆さんのサポートに全力で取り組んでいく。マイナ保険証への円滑な完全移行に向け、皆さんと力を合わせて前進していきたい。
本日は、令和7年度の事業計画および各会計の予算案を諮る。理事各位の活発な審議をお願いして、私のあいさつとする。