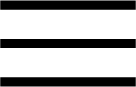健保ニュース
健保ニュース 2024年6月下旬号
令和5年人口動態統計
出生数72万人 出生率は過去最低の1.2
厚生労働省は5日、令和5年人口動態統計月報年計(概数)を取りまとめ、公表した。
それによると、5年の出生数は72万7277人で、調査を開始した明治32年以降、過去最少となった。前年に比べ4万3482人減となり、8年連続で減少した。
1人の女性が一生の間に産む子供の数を表す合計特殊出生率は1.20で調査を開始した昭和22年以降、過去最低となった。前年から0.06ポイント下がり、8年連続で低下した。
都道府県別にみると、沖縄県が1.60、長崎県と宮崎県が1.49と高い一方、東京都が0.99、北海道が1.06、宮城県が1.07と低く、西高東低の傾向にある。東京都は、調査開始以降で初めて1ポイントを下回り、過去最低となった。
母の年齢階級別の出生数は、「45歳以上」を除くすべての階級で減少。第1子出生時の母の平均年齢は31.0歳で2年ぶりに上昇した。
厚労省は、出生数や合計特殊出生率が下がり続ける背景について、「経済的不安や子育てと仕事の両立の難しさなど、個々人の結婚や出産、子育ての希望の実現を阻む様々な要因が複雑に絡み合っている」と説明した。
一方、死亡数は157万5936人で同6886人増となり、3年連続で増加した。年齢別にみると75歳以上が全体の7割を超えている。
死因別の死亡数は、悪性新生物〈腫瘍〉が最も多く38万2492人となり、全体の24.3%を占めた。次いで心疾患(高血圧性を除く)が23万1056人(全体の14.7%)、老衰が18万9912人(同12.1%)、脳血管疾患が10万4518人(同6.6%)と続く。
なお、令和5年から「新型コロナウイルス感染症」を死因項目に追加。死亡数は3万8080人(同2.4%)だった。
年齢別死因は、悪性新生物が男性の「5~9歳」と「45~94歳」、女性の「5~9歳」と「35~89歳」で多く、自殺が男性の「10~44歳」、女性の「10~34歳」、老衰が男性の「95歳以上」、女性の「90歳以上」でそれぞれ多くなっていた。
出生数と死亡数の差である自然増減数は過去最大の84万8659人減で前年比5万368人の減少となり、17年連続で減少幅の拡大が続き、人口減に歯止めがかからない。
婚姻件数は同3万213組減の47万4717組となり、過去最低。人口千人当たりの婚姻率は3.9で前年より低下している。
離婚件数は同4709組増の18万3808組となり、増加に転じた。人口千人当たりの離婚率は1.52で、前年より上昇した。
厚労省は、調査結果に対して、「少子化の状態は危機的状況にあり、若年人口が急激に減少する2030年代までのこれからの6年間が少子化傾向を反転できるラストチャンス」と捉え、少子化対策は待ったなしの瀬戸際にあるとの見解を示した。
調査は、人口および厚生労働行政施策の基礎資料を得るために実施しているもので、令和5年の1年間に日本で発生した日本人の事象が調査客体。今回の発表は各月の数値を合計した概数で、これに修正を加えたうえで9月に確定数を公表する。