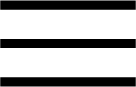健保ニュース
健保ニュース 2024年6月下旬号
医療部会でかかりつけ医機能報告を議論
河本専務理事 症状の報告は不可欠
社会保障審議会医療部会(遠藤久夫部会長)は7日、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向け、委員から意見を聴取した。
この日の会合では、厚生労働省が、かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に向けた検討状況について報告。
令和7年度から創設する「かかりつけ医機能報告制度」で報告を求める機能の内容について、①一定以上の症状(35項目のうち20項目以上)に対して一次診療を行える②17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行える③かかりつけ医機能研修の修了者および総合診療専門医の有無─などが、厚労省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」で議論されているとした。
健保連の河本滋史専務理事は、「患者が医療機関を選択する際に役立つものでなくては、かかりつけ医機能報告の制度整備が目的を果たしたとは言えない」と発言。そのうえで、「報告において、一定以上の症状に対し、一次診療が可能であることは不可欠な要素」として、①が妥当との考えを示した。
かかりつけ医機能報告制度により地域の実態を見える化し、かかりつけ医の条件を満たす医療機関が増えていくことが患者の選択につながると強調した。
山口育子委員(ささえあい医療人権センターCOML理事長)は、報告を求める機能の内容について、「患者の選択に資する情報としては、診療領域より症状の方が分かりやすい」と発言。
診療領域の報告が望ましいとの意見に対しては、「そもそも診療所等には標榜科目が存在しており、それ以外の診療領域を報告することになる」として、患者が混乱する可能性を指摘した。
佐保昌一委員(日本労働組合総連合会総合政策推進局長)は、「国民・患者の安心につながる観点から、一定の診療経験がある場合でも、かかりつけ医機能に関する研修は必要」との考えを示した。
一方、城守国斗委員(日本医師会常任理事)は、かかりつけ医機能報告制度について、「各地域で必要なかかりつけ医機能を医療機関等の連携により把握し、しっかりと確保することが最終目的」と言及。
そのうえで、「患者の考える症状と医師の考える症状には大きな差があり、症状の出ている疾患は非常に多岐にわたる場合が多い」と指摘し、診療領域による報告を求めた。