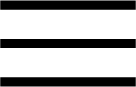健保ニュース
健保ニュース 2024年6月中旬号
子子支援法が可決・成立
8年度に支援金制度創設
岸田首相 国民の理解・納得を促進
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」は、5月30日の岸田文雄首相への質疑を経て、6月4日の参院内閣委員会(阿達雅志委員長)で可決。翌日の5日に参院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で政府原案どおり可決、成立した。
自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党の4会派共同提案による附帯決議が付された。
岸田首相は5月30日の参院内閣委員会の質疑で、「子ども・子育て支援金制度」への国民の理解・納得を促進する観点から、歳出改革等による社会保障負担率の低下を確かなものにしていくと強調した。
同法は、「こども未来戦略」の「こども・子育て支援加速化プラン」に盛り込まれた子育て支援の施策や児童手当の給付などの拡充と財政基盤の確保の一体的な整備をめざすもの。一部を除き令和6年10月1日に施行する。
財源の一部に、社会保険制度を通じて拠出する「子ども・子育て支援金制度」を創設。歳出改革と賃上げによって社会保険負担軽減の効果を生じさせ、その範囲内で支援金制度を構築することで、実質的な負担が生じない財政構造が示されている。
支援金制度は、8年度から段階的に実施。医療保険の被保険者や事業主が負担する額は、8年度に6000億円、9年度に8000億円、「加速化プラン」が完了する10年度に1兆円を見込む。
医療保険者は、医療保険料や介護保険料と合わせて、子ども・子育て支援金を徴収することになる。健康保険法上は、一般保険料率と区分して子ども・子育て支援金率を規定。子ども・子育て支援金率は、政令で定める率の範囲内で保険者が定めるとされているが、被用者保険間の按分は総報酬割であることを踏まえ、実務上、国が一律の支援金率を示す扱いになる。施行日は8年4月1日。
こども家庭庁は、支援金の加入者1人当たり負担額の試算を公表しており、10年度は平均月額450円で、医療保険料の4%程度の規模になると見込む。健保組合は同500円で、被保険者1人当たりでは同850円になると試算した。
さらに被用者保険において所得別に被保険者1人当たり負担額を試算すると、10年度の平均月額は、▽年収200万円で350円▽同400万円で650円▽同600万円で1000円▽同800万円で1350円▽同1000万円で1650円─になる。
支援金制度の構造
財源のあり方が論点に
6月4日の法案採決では、自民、公明両党の賛成多数で可決。自民党、立憲民主党、公明党、国民民主党の4会派共同提案による附帯決議が付された。
野党は、医療保険料に上乗せして拠出する「子ども・子育て支援金制度」を財源とする法案に一貫して反対し、質疑を通して財源のあり方の再考を求めてきた。この日は、質疑終局後、原案に反対の立場から討論を行った。
鬼木誠氏(立憲民主党)は、支援金制度は社会保険の目的外使用に当たり、「増税批判を避けるために取りやすいところから取る制度」と断じ、「実質的な負担が生じないという説明はまやかしだ」と訴えた。片山大介氏(日本維新の会)は、「現役世代に最も重くのしかかる社会保険料を財源にすることで少子化を加速させるのは疑いようもない」と指摘した。
参院の審議では、与党からも支援金制度創設に対する世論の受け止めや医療保険制度を活用する理由が質されるなど子ども・子育て財源のあり方が論点となり、成立後も国民理解の醸成という課題が残る。
参院における審議は、内閣委員会の5月21日、23日の質疑、23日の参考人招致、28日の厚生労働委員会との連合審査会開催を経て、30日、6月4日と審議を重ね、審議時間は計20時間15分、参考人質疑を含め23時間35分となった。