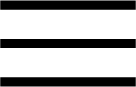健保ニュース
健保ニュース 2024年6月上旬号
新地域医療構想検討会がヒアリング
河本専務理事 患者が必要な医療を提供
さらなる機能分化・強化を
厚生労働省の「新たな地域医療構想等に関する検討会」(座長・遠藤久夫学習院大学長)は5月22日に、新たな地域医療構想に関する検討の一環として、関係団体・有識者ヒアリングを実施した。会合では、健保連の河本滋史専務理事が保険者の立場から意見を述べ、2040年頃の医療を想定するうえで、人口構造の変化や財政的制約の深刻化などは「避けて通ることはできない」と指摘。患者が必要な時に、迅速に必要な医療を受けられるよう、さらなる医療機能の分化・強化、連携を進め、過不足のない最適な医療提供体制を構築することを要望した。
河本専務理事は、「病床数は見込みどおり必要量に収斂している」と述べ、地域医療構想の取り組み成果として評価。医療資源投入量に着目して需要を推計し、計画的に調整を行う手法は妥当との考えを示した。
一方、必要量との乖離に対する要因把握ができていないケースの精査が課題と指摘。2025年に向け、この2年間は、新たな地域医療構想の発射台として極めて重要と強調した。
他方、2040年頃を見据えた医療のあり方を想定するうえで、▽人口構造の変化▽医療需要の変化▽医療の高度化▽医療・介護人材の不足▽医療DX等の推進▽国民・患者の変化▽財政制約の深刻化─は「避けて通ることはできない」と指摘。
そのうえで、「患者が必要な時に迅速に必要な医療を受けられることが一番の肝になる」との見解を示し、さらなる医療機能の分化・強化、介護を含めた連携により、過不足のない最適な医療提供体制を構築することを要望した。
2040年頃を見据えた
医療提供体制を例示
河本専務理事は、2040年頃を見据え、3つの圏域①中学校区~市町村②市町村~二次医療圏③二次医療圏~都道府県─を前提とし、②が①を、③が②を包摂する地域的な広がりのある医療提供体制のイメージを例示した。地域の実情に応じ、圏域範囲を調整する必要性にも言及。
さらに、圏域における重層的な役割分担を明確化することを盛り込んだ。
①は、かかりつけ医が患者を中心に医療・介護にかかる調整を行い、日常的な外来と在宅を充足する「顔の見える関係」を構築する。
②は、救急搬送を含めた一般的な入院を充足し、紹介患者を中心とする専門外来、時間外診療や在宅医療不足を補完する「まさかの時の支え」となる体制を確保する。
③は、地域医療の「最後の砦」として、基幹病院・拠点病院が濃密な医療を集中投入し、重度の救急搬送やがんなどの難しい手術を集約、難病など専門性が極めて高い特殊な外来に専念するものと位置づけた。
合わせて、外来・在宅・入院の観点から求められる体制を提言した。「外来」では、患者数が減少する一方、臓器別・診療科別に特化した診療所が増加することは非効率と指摘。得意領域を持ちつつ、日常的な症状に幅広く対応する「かかりつけ医機能」の強化を重要視した。
「在宅」では、入院並みの重装備型と日常診療にとどまる軽装備型でアプローチが異なると指摘。軽装備型を外来のかかりつけ医が担当することで、在宅医療の裾野を拡大していくことを提案した。
「入院」は、最適な病床・病棟の配置に向け、引き続き再編・統合を進めるよう要請した。
新たな地域医療構想には、医療需要の適切な推計などとともに、患者の希望による選択や保険者機能の発揮が推進されることで、患者にとって安全・安心な医療・介護が効果的・効率的に提供されることを期待した。
このほか、医療機関の立場から、伊藤伸一構成員(一般社団法人日本医療法人協会会長代行)が意見陳述し、公的医療機関等の再編統合には、地域医療構想調整会議の活性化が不可欠と指摘した。
地域の現状や将来像を踏まえ、医療機関のダウンサイジングや機能の分化・連携、集約化、機能転換・連携などを念頭に検討を進めるべきと言及。統合にあたっては、地域の医療提供のあり方に不適切な影響を与えることがないよう、関係者を含めた十分な協議を行うことが重要と提言した。