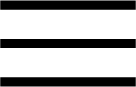健保ニュース
健保ニュース 2024年6月上旬号
かかりつけ医機能報告など
分科会が各論の検討に着手
対応可能な診療の報告 症状と診療領域で二分
厚生労働省の「かかりつけ医機能が発揮される制度の施行に関する分科会」(永井良三座長)は5月24日、今夏の取りまとめに向け、各論の検討に着手した。
この日の会合では、厚生労働省が、前回4月12日の会合を踏まえ、①施行に向けて省令やガイドライン等で定める必要がある事項②かかりつけ医機能が発揮されるための基盤整備、国の支援のあり方─を提案。
このうち、①は、令和7年4月に創設する「かかりつけ医機能報告制度」について、継続的な医療を要する者への発生頻度が高い疾患にかかる診療その他の日常的な診療を総合的かつ継続的に行う「1号機能」の有無と内容の報告を求める。
「1号機能」の「具体的な機能」は、「継続的な医療を要する者に対する発生頻度が高い疾患にかかる診療を行うとともに、継続的な医療を要する者に対する日常的な診療において、患者の生活背景を把握し、適切な診療および保健指導を行い、自己の専門性を超えて診療や指導を行えない場合には、地域の医師、医療機関等と協力して解決策を提供する機能」と位置づけた。
「1号機能」にかかる報告事項として厚労省は、「案1」~「案3」を提示。「案1」は「一定以上の症状(臨床研修の到達目標の頻度の高い症状35項目のうち、必修20項目)に対して一次診療を行うことができること」とした。
「案2」は、▽「具体的な機能」を有することおよび報告事項について院内掲示により公表している▽かかりつけ医機能に関する研修の修了者がいる、または総合診療専門医がいる▽17の診療領域ごとの一次診療の対応可能の有無、いずれかの診療領域について一次診療を行うことができる▽17の診療領域ごとの患者からの相談の対応可能の有無、いずれかの診療領域について患者からの相談に応じることができる─ことと整理。
「案3」は、▽「具体的な機能」を有すること、および報告事項について院内掲示により公表していること▽かかりつけ医機能に関する研修修了者の有無、受講者の有無、総合診療専門医の有無─とした。
「案1」~「案3」が「可」の報告の場合は「1号機能を有する医療機関」として「2号機能」の報告を求める。
「2号機能」の有無と内容は、(1)通常の診療時間外の診療(2)入退院時の支援(3)在宅医療の提供(4)介護サービス等と連携した医療提供─で、(1)は自院における「時間外対応加算1~4」の届出・算定状況などを報告事項とした。
かかりつけ医機能報告の報告を行う対象医療機関は、特定機能病院および歯科医療機関を除く病院・診療所で、都道府県は、▽1号機能および2号機能について医療機関から報告された事項▽2号機能の体制の確認結果▽地域の協議の場で協議を行った結果─を公表する。
厚労省は、「かかりつけ医機能報告」を「医療機能情報提供制度」にもとづく報告と合わせて行えるよう、同制度と同様、医療機関による定期報告を毎年度の1~3月とするスケジュールを提案した。
他方、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明については、「自院において、継続的な医療を要する者に対して在宅医療や外来医療を提供する場合であって、概ね4か月以上継続的に医療の提供が見込まれる場合」に努力義務とする。
説明内容は、▽当該患者に対して発揮するかかりつけ医機能(1号機能等)▽病院、診療所の管理者が患者への適切な医療提供のために必要と判断する事項─と整理した。
適切な診療に支障を及ぼすおそれがある場合や、人の生命、身体、財産に危険を生じさせるおそれがある場合は、説明の努力義務を免除することとした。
厚労省が提案した「かかりつけ医機能報告」による報告・公表について、健保連の河本滋史専務理事は、「かかりつけ医機能報告の最大の目的は、国民・患者のより適切な医療機関の選択に資することにある」と強調し、「どの医療機関がどんな症状に対応できるのかが明確になれば、保険者が加入者にわかりやすい情報を発信し、患者が医療機関を選ぶ際にも効果的だ」と発言。
こうした観点や総合的な診療を十分に担保するために、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の明確化に向けた「1号機能の有無と内容」について、「一定以上の症状に対して一次診療を行うことができること」を報告する「案1」が望ましいとの考えを示した。
また、「2号機能の有無と内容」で報告事項とされた「時間外対応加算の届出・算定状況」について、「時間外加算」、「深夜加算」、「休日加算」の実績も報告するよう要望した。
土居丈朗構成員(慶應義塾大学経済学部教授)も、全世代型社会保障構築会議の報告書に明記された「日常的に高い頻度で発生する疾患・症状について幅広く対応」を体現するならば、「案1」のように「一定以上の症状に対して一次診療を行うこと」を要件とするのは理に適っているとの認識を示し、「何らかの形で症状の報告を求めることは必須だ」と言及した。
一方、城守国斗構成員(日本医師会常任理事)は、「制度設計によっては、フリーアクセスを一定程度、制限することにもなりかねない」と述べ、「初期は、現在の診療領域に対応する形が良い」と主張した。
このほか、河本専務理事は、「かかりつけ医機能を有する医療機関」の患者への説明で努力義務とされた「4か月以上継続的に医療の提供が見込まれる場合」の提案については、「患者のニーズによって、もう少し短い期間でも対応してほしいケースも考えられる」と指摘し、運用の実態を踏まえて期間の見直しを検討する必要があるとの考えを示した。
同分科会は、今夏の取りまとめに向け、引き続き、各論の検討を進めていくこととした。