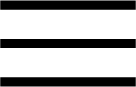健保ニュース
健保ニュース 2024年6月上旬号
財政審が骨太反映へ「建議」
歳出目安の下で歳出改革継続
新創加算累積控除等 毎年薬価改定は完全実施
財政制度等審議会(十倉雅和会長)は5月21日、政府が6月を目途に策定する「骨太方針2024」への反映に向け、「我が国の財政運営の進むべき方向」に関する基本的考え方を提言した「建議」を鈴木俊一財務大臣宛てに提出した。社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加相当分におさめる「目安」の下で歳出改革の取り組みを継続していくことが必要不可欠と強調。医療分野では、令和7年度の毎年薬価改定で、新薬創出等加算の累積額控除など既収載品の算定ルールをすべて適用するよう提言したほか、セルフメディケーションの推進と整合的な保険給付範囲の見直しなどを求めた。
財政制度等審議会の「建議」は、例年、春と秋の2回にわたり、財政健全化に向けた考え方や今後の財政運営、次年度の予算編成に関する考え方をまとめ、財務大臣に要請している。
「春の建議」は、「我が国の財政運営の進むべき方向」として、持続可能な財政構造の構築に向け取り組んでいくことが必要と指摘。2025年度の国・地方のプライマリーバランス黒字化などの財政健全化目標の実現に向け、規律ある「歳出の目安」の下で歳出改革の取り組みを継続すべきと提言した。
政府が令和3年6月に閣議決定した「骨太方針2021」は、2022年度から2024年度までの3年間、社会保障関係費の実質的な伸びを高齢化による増加相当分におさめる目安に沿った予算編成を行うと明記し、歳出改革努力を継続してきた。
これに対し、今回の「春の建議」は、2025年度以降も規律ある「歳出の目安」の下で歳出改革の取り組みを継続していくことが必要不可欠と訴えた。
薬剤自己負担のあり方
保険外併用と合わせ検討
団塊の世代がすべて後期高齢者となる2025年以降も後期高齢者は引き続き増加が見込まれる一方、生産年齢人口は急速な減少を続ける結果、社会保障制度の支え手たる現役世代の負担がより重くなると見通した。
このため、社会保障の持続可能性を確保する観点から、引き続き、女性や高齢者の就労促進を進めながらも、全世代型社会保障の構築に向けた改革に取り組む必要があると強調した。
さらに、社会保障の持続性確保の観点からは、社会保険料の負担にも目配りする必要があると指摘。若者・子育て世帯の手取り所得を増加させるとともに、「こども未来戦略」にもとづき給付の適正化等を通じて医療・介護の保険料率の上昇を最大限抑制すべきと訴えた。
社会保障にかかる現役世代の負担は今後も増加が見込まれ、マクロの視点から医療・介護にかかる保険料率の上昇を最大限抑制するために、効率的で質の高い医療・介護サービスを確保しつつ、給付の適正化を図るべく、「改革工程」に記載されたミクロの改革項目を着実に実施していく必要があるとした。
医療分野では、今後加速する「支え手(現役世代)」の減少や、イノベーション等による医療の高度化・高額化の視点を踏まえると、質の高い医療を提供しつつ、国民皆保険の持続可能性を確保していくための医療制度改革を確実に実施しなければならないと明記。
政府は国民に対して、医療保険制度の「あるべき姿」を示すとともに、現行制度にメスを入れなければ制度の持続可能性が失われ、継続自体が困難になるという未来を明確に示したうえで制度改革に対する理解を醸成する必要があるとした。
令和7年度の毎年薬価改定に向けては、「2年に1度しか適用されないルールがあるのは合理的な説明が困難」と指摘し、新薬創出等加算の累積額控除や長期収載品の薬価改定など既収載品の算定ルールをすべて適用するよう提言。
また、費用対効果評価を実施する薬剤の範囲や価格調整対象範囲を拡大するとともに、費用対効果評価の結果を保険償還の可否判断にも用いることも検討すべきとした。
医療提供体制は、医師の地域間、診療科間、病院・診療所間の偏在是正に向けて、診療所の報酬適正化のほか、地域別診療報酬を活用したインセンティブ措置を検討し、診療所過剰地域と不足地域で異なる1点当たり単価を設定するなど、報酬面からも医療資源のシフトを促すべきとした。
保険給付範囲の見直しでは、セルフメディケーションの推進、市販品医薬品と医療用医薬品とのバランス、リスクに応じた自己負担の観点等を踏まえ、OTC類似薬に関する薬剤の自己負担のあり方について、保険外併用療養費制度の柔軟な活用・拡大と合わせ検討すべきと明記。
また、諸外国の例も踏まえ、医薬品の有用性が低いものは自己負担を増やす、あるいは、薬剤費の一定額まで自己負担とする対応を検討するよう求めた。
後期・現役並み所得者
判定基準の見直しを
75歳以上の1人当たり医療費は現役世代の約4倍に達し、その8割強が公費と現役世代の支援金で賄われる構造となっているなか、現役世代は医療費の8割を患者負担と保険料で賄いつつ、後期高齢者支援金も負担していると問題提起した。
このため、年齢ではなく能力に応じた負担とし、世代間の公平性を確保する観点から、「改革工程」にもとづき、医療保険・介護保険の保険料や窓口負担の判定における金融所得の勘案、金融資産等の取り扱いについて検討を深めるべきとの考えを盛り込んだ。
3割負担となる後期高齢者・現役並み所得者の判定基準については、現役世代との公平性を図り、一定の仮定を置いた世帯収入要件について見直しを行うべきと提言した。
介護分野では、▽保険給付の効率的な提供▽保険給付範囲のあり方の見直し▽高齢化・人口減少下での負担の公平化─という視点から、介護保険制度の持続性確保のための見直しを「改革工程」に沿って遅滞なく進めることで、中長期的に増大する介護需要に応えられる体制を構築していく必要があるとした。
利用者負担については、負担能力に応じて増加する介護費をより公平に支え合う観点から、所得だけでなく、金融資産の保有状況等の反映のあり方や、きめ細かい負担割合のあり方と合わせて検討したうえで、2割負担の対象範囲拡大について早急に実現するよう提言。
また、医療保険と同様に、利用者負担を原則2割とすることや現役世代並み所得(3割)の判断基準の見直しも検討していくべきとの考えを示した。
年金分野では、被用者保険の適用拡大について、勤労者皆保険を徹底する観点から次期年金制度改革で、20時間未満労働者への適用について道筋をつけるべきと明記。
また、被用者保険では106万円および130万円の年間収入の各水準として指摘されている「年収の壁」について、次期改革で制度的対応を実現する必要があるとした。