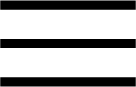健保ニュース
健保ニュース 2024年6月上旬号
幸野参与がシンポジウムで講演
生活習慣病管理の改革を提言
薬剤師管理下 医療用薬をOTC薬で処方
健保連の幸野庄司参与は、5月26日に開催された「第18回学術大会日本ジェネリック医薬品・バイオシミラー学会」の「スポンサードシンポジウム1(OTC医薬品分科会創設の意義と新たなOTCの開発・提供・普及促進に向けて)」で、「医療保険制度改革とOTC医薬品の役割」をテーマに講演した。
高齢化のピークを迎える2040年問題は、医療保険制度の構造改革なくして乗り超えられないと問題提起し、持続可能な国民皆保険制度の構築に向けて、あらゆる分野で聖域なき改革が不可欠と強調。
生活習慣病の疾病管理のあり方として、状態が安定し、自己管理できるなど一定の条件を満たす患者について、特例的に医療用医薬品を薬剤師の管理のもとにOTC医薬品として処方する改革を提言した。
幸野参与は、健保連の推計から、高齢化のピークを迎える2040年の国民医療費は現在の約1.5倍となる70億円を超えるとの見通しを示し、医療費の約3分の1を占める生活習慣病の疾病管理のあり方に着目した医療保険制度改革の必要性を訴えた。
生活習慣病と疾病管理の現状として、▽外来通院患者の上位は高血圧症、糖尿病、脂質異常症で年々増加傾向▽疾病管理は病状の継続管理、食事、運動等の指導および薬物療法が主▽6か月以上同じ薬の処方が繰り返されている「長期Do処方」の患者割合(延べ処方日数ベース)は40歳以上で約半分▽「長期Do処方」を診療所で受けた患者は約4割が月1回の受診(処方日数の間隔が受診間隔)▽令和4年度に導入されたリフィル処方は1%未満と限定的─と提示。
そのうえで、▽生活習慣病は患者の状態、生活習慣、自己管理意識によって疾病管理のあり方を変えるべき▽その方法として、対面診療、オンライン診療、長期処方、リフィル処方がある▽一定の条件を満たす患者に対しては、特例的に医療用医薬品を薬剤師の管理のもとにOTC医薬品として処方することを可としてはどうか─と疾病管理のあり方について選択肢を示した。
生活習慣病の疾病管理を、①現行の長期Do処方(月1回通院30日処方)②リフィル処方(1回/3月通院)③対面(1回/6月通院)+特例OTC(毎月薬局でOTC購入)④特例OTC(毎月薬局でOTC購入)─と整理。
このうち、③は、▽状態が安定し、自己管理(服薬・食事・運動等)ができることを条件にOTC処方とする▽状態の継続管理は医師から薬剤師にシフトする(かかりつけ医とかかりつけ薬剤師の連携必要)▽現在の医療用医薬品を条件付きOTC医薬品とし、かかりつけ薬局で限定販売─と提案した。また、④は③に加え、「かかりつけ薬剤師は必要に応じ、かかりつけ医への受診勧奨を行う」こととした。
高血圧症の年間医療費(患者負担)は、①9万7680円(2万9280円)②5万5760円(1万6720円)③1万480円(1万9140円)④0円(1万8000円)─と推計。
日本における高血圧有症者約2450万人のうち、仮に1割(約245万人)の患者がOTC管理に移行する場合、年間で約237億円の医療費適正化効果が見込まれると強調した。
幸野参与は、「皆保険の各ステークホルダーが真剣に考える時にきている」と言及し、③の実現に向け、厚生労働省に高血圧症を対象とした特区による実証実験を実施するよう提言。
また、「長期Do処方」が行われている患者への当該仕組みの勧奨などを保険者のミッションとして位置づけた。