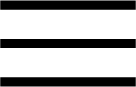健保ニュース
健保ニュース 2024年6月上旬号
松本理事が6年度診療報酬改定を総括
外来医療で患者負担低減を期待
リフィル処方 理解促進が課題
中央社会保険医療協議会の支払側委員を務める健保連の松本真人理事は、本誌のインタビューに応じ、令和6年6月1日に施行された6年度診療報酬改定について、「診療報酬は診療行為への対価だと主張し続け、データやエビデンスにもとづく議論を求めてきた」と2回目となる改定論議を振り返った。外来医療は、支払側が提案した「生活習慣病に対応する医学管理料の再編」による医療の質向上と患者負担の低減を期待するとともに、リフィル処方の活用を推進するアプローチが盛り込まれた対応を評価した。また、健保組合に向けたメッセージとして、自身の受ける医療に興味を持ってもらえるよう、理解しやすく伝える努力をし続けていくと語った。
─中医協における令和6年度診療報酬改定の議論を振り返って。
議論の半ばで委員に就任した前回の令和4年度改定とは異なり、最初から委員として議論に参加した。
そのなかで、中医協の前日の夕方に支払側の委員の皆さんと情報共有し、支払側の総意としての意見を発信できるよう気を配った。
かねてより「肌感覚でなく、事実にもとづいて判断すべき」との認識で、データやエビデンスにもとづく議論を求め、厚生労働省から前向きな資料を提出してもらった。
─令和6年度診療報酬改定率について。
支払側は、「診療報酬を引き上げる環境にはない」と強く主張してきたものの、診療報酬本体は令和4年度の改定率と比較するとほぼ2倍の水準となった。
特に、議論の途中から、賃上げや物価高騰に焦点が当たるようになってしまった。長いデフレ下でも原則プラス改定が続いたことや、医療費が増加し続けるなかで、足下の経済動向に着目して対応することに疑問は残るが、政府の判断として、サービス提供の土台のように捉えられたと受け止めている。
─賃上げ・基本診療料等の引き上げについて。
賃上げは今回改定の大きなテーマとなり、初再診料や入院料等の引き上げと「ベースアップ評価料」の新設という2つの方法が取られた。
支払側は、過不足のない財源配分や詳細な検証が難しいなどの観点から基本料の引き上げに対し、「望ましくない」と主張してきたが、賃上げ対象職種に臨時雇用や派遣勤務も含まれ、医療機関による計画的な処遇改善が困難なこともあり、やむを得ず応じることとなった。一方、「ベースアップ評価料」については、非常に細かく制度設計され、支払側の要望に近いものになった。
今回の診療報酬上の対応は、しっかりと賃上げに充ててほしい。健保連としては、そもそも賃上げは経営者のマネジメントでやるべきだと主張し続けてきた。
基本料の引き上げや評価料の新設が妥当な対応だったのか、検証を必ず実施しなくてはならない。
医療経済実態調査の結果から、コロナ補助金を含めれば医療機関の経営は危機的な状況と言えず、長期借入等の固定負債が減少さえしている。特に診療所は堅調で、病院と経営実態に差がある。引き続き医療機関の経営にも注視していきたい。
─入院医療の見直しについて。
「急性期一般入院料1」の「重症度、医療・看護必要度」は今改定でも公益裁定となった。
支払側は、病床機能の分化・強化や連携を推進する観点から、「急性期一般入院料1」を算定している病院における患者の状態や医療資源投入量等のデータをエビデンスとして、実態に見合った診療報酬をセットし、急性期病床を集約するよう主張してきた。一方で診療側からは、「経営に影響がある」などの意見が盛んに出された。公益裁定により、地域医療に配慮しつつも、賃上げ対応による入院料の引き上げや「地域包括医療病棟」の新設も踏まえ、急性期病床を重点化し、病床機能の転換につながる形になったと理解している。
また、「地域包括医療病棟」の新設については、支払側は当初、新たな病棟の新設ではなく、既存の「地域包括ケア病棟」での高齢救急患者の受け止めを主張してきた。
これに対し、診療側から「13対1看護配置の病棟では受け止めきれない」との指摘があり、厚労省が新たな病棟を提示した経緯がある。今後、「地域包括医療病棟」が高齢者救急をはじめとする複合的なニーズを併せ持つ患者に役立つことを期待しつつ、運用状況についても注視していきたい。
他方、「回復期・慢性期」は、適正化を図りながら、従来持っている機能をしっかり果たしていくことが重要と考える。
「回復期」では、回復期リハビリテーション病棟に上乗せされている加算の廃止や、地域包括ケア病棟の入院日数に応じた評価体系の導入、「慢性期」では、医療資源の投入量に応じた評価の精緻化により、一定の適正化を図ることができたと認識している。
─外来医療の見直しおよび同時報酬改定への対応について。
生活習慣病の計画的な医学管理に対する評価が、支払側からの提案で再編されることになった。糖尿病、高血圧、脂質異常症は長く付き合わなくてはならない疾病で、単に薬を飲むだけでなく、運動や食事が重要になる。算定要件が曖昧な「特定疾患療養管理料」の対象からこの3疾患を除外し、患者の同意を得て療養計画書を作成することが必須の「生活習慣病管理料」に一本化することで、適切な医学管理が期待できる。さらに、生活習慣病管理料の要件として学会ガイドラインの参照を強く求めることになり、医療の質が高まるものと考える。
一方、これまで生活習慣病管理料には検査料等が包括された点数区分のみで、そもそも医療費が高いうえに、同様に計画的な医学管理を評価する「外来管理加算」の併算定が可能で、ますます医療費が高くなる仕組みだった。そのため、生活習慣病管理料に検査料等が出来高の点数区分を新設するとともに、外来管理加算の併算定を廃止することになり、特定疾患療養管理料に比べて医療費を抑えることになった。また、従来からある包括の点数区分については、電子カルテ情報共有サービス等を活用した療養計画書の簡素化により、医師の負担が軽減されることも想定し、適正化を図ることができた。さらに、月1回以上の治療管理が必須だったのを見直し、リフィル処方や長期処方に対応可能なことを施設基準に追加した。通院回数を減らすことで、患者の費用負担と身体負担の両方が軽減されるものと考える。
リフィル処方や長期処方への対応については、かかりつけ医機能と関連する地域包括診療料等の施設基準にも規定された。リフィル処方は、令和4年度改定で具体的な適正化の数値なども盛り込まれたが、現実問題として進んでいない。最終的に医師の判断とは言え、患者から申し出ないとなかなか進まないと認識しており、健保組合による、加入者への理解促進などもさらに進める必要がある。保険者として、加入者にしっかり周知するとともに、医療従事者からも患者に説明するなど、少しでも加入者・患者の負担が低減する適切な運用に向け、努力していかねばならない。
生活習慣病の医学管理やリフィル処方・長期処方については、今回の改定で終わりではなく、医療の質を維持・向上しつつ、患者の通院負担や費用負担の軽減につながるよう、状況を見ながら、引き続き修正すべきと考えている。
「同時報酬改定」への対応では、支払側、診療側、そして厚労省も6年に1度の機会を意識し、特に介護との連携をどのように進めるのかといった議論のなかで、医療と介護の役割分担をしたうえで、介護施設で不足する医療サービスを速やかに提供できるよう、介護施設に対する協力医療機関の役割強化や、かかりつけ医が介護関係者にしっかり対応してもらうための要件や評価のあり方について議論した。
診療報酬と介護報酬でそれぞれ改定の議論に入る前の昨年春、医療と介護の関係者による意見交換会があり、そこに保険者の立場で参加した。医療・介護連携については、これまでも推進されてきたが、実態が伴っていないことをひしひしと感じた。そのため、今回の同時改定が真の連携につながることを期待している。
─医療DXの推進について。
従来、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」があり、それを今回「医療情報取得加算」に見直しつつ点数設計も見直した。
医療DXはこれからが本番で、大きな柱となる「電子カルテ情報共有サービス」などを進めなくてはならないが、それには医療機関側の設備の導入、改修、維持等が必要で、そのために、「医療DX推進体制整備加算」が新設されたと認識している。算定要件の一部は経過措置が講じられるが、医療機関にはしっかり導入・運用してもらいたい。
「マイナ保険証」への移行は健保連も力を入れており、間違いなく推進しなくてはならない。ただし、これは医療DXの取り組みの一環であり、医療機関や患者に行動変容が生じないと、医療の質向上や効率化という本来の目的が果たせない。例えば、単なる受付業務の簡素化だけでなく、患者がマイナ保険証で常に受診し、医師がオンライン資格確認等システムを活用し、過去の病歴や服薬状況を見ながら診断するなど、診察行為につながって、はじめて医療DXの意味がある。医療の質の向上をどこで捉えるかは人それぞれだが、まずは患者が1つでもメリットを実感できることが重要だ。
─感染症対策について。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け、今後、同様の感染症が発生した場合に向けて、都道府県知事と医療機関が協定を締結することが感染症法の改正で定められた。診療報酬上の対応として「感染対策向上加算」や「外来感染対策向上加算」に協定締結を要件化したほか、「発熱患者等対応加算」も新設し、感染症への対応が強化された。様子を見る必要はあるが、少なくとも診療報酬上の対応は十分にできたと考えている。
─歯科報酬の見直しについて。
今回、歯科技工士をはじめとする関係者への賃上げに向け、医科と同様に初再診料が引き上げられたと認識している。
「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の施設基準の名称、要件および評価の見直しは、現在の、「虫歯になったから治療するのではなく、定期的な口腔管理を実施していく」との動きのなかで、どのような形で診療報酬により対応していくかの表れと認識している。国民皆歯科健診のような動きが進んでおり、こうした傾向はさらに顕著になっていくと考えている。
─調剤報酬の見直しについて。
全体的に調剤に関する考え方では、調剤件数が多く経営効率の高い門前薬局や敷地内薬局には厳しく、地域のなかで奮闘している薬局に対しては、医薬品の供給拠点機能や対人業務を評価するスタンスで対応している。とりわけ新たなビジネスモデルとして確立されてきた敷地内薬局については、「特別調剤基本料」をさらに引き下げたが、今後は従来の手法だけでは対応が難しくなってくると認識している。地域で役割を果たせない薬局の評価は少しずつ下がり、どの薬局にも一律の報酬とはならない。大手のチェーン薬局などが「かかりつけ薬局」として、24時間、祝日も対応していけるかということが議論の俎上にあがってくると考えている。
一方で、「地域支援体制加算」については、薬局が地域を支えていく観点から、拠点としての役割を果たす薬局を適切に報酬で手当てするために見直しを行った。今回の見直しが、チェーン薬局が地域でどのような役割を果たすのかという議論の契機になることを期待する。
─長期収載品の保険給付範囲見直しについて。
後発医薬品を使用できるにもかかわらず、患者が敢えて長期収載品を選択する場合には、ある程度の自己負担を求める選定療養の仕組みが10月から導入される。最終ゴールは後発医薬品への移行と理解している。患者負担が増えないように保険者としても新たな仕組みを加入者に周知するが、医療現場においては薬剤師による患者への説明が非常に重要になるため、業務負担に対する一定の加算も認めることになった。
後発医薬品の使用促進については、政府目標として数量割合に加え金額割合なども設定されており、引き続き動向をフォローしたい。長期収載品の選定療養がどの程度医療費に影響するかは正確に見通せないが、新薬のイノベーションや後発医薬品等の安定供給に向けた対応の財源になっている側面もあり、しっかり効果を把握する必要があると考える。
─ビタミン剤、湿布等の保険給付範囲の見直しについて。
患者の立場からはOTC医薬品を購入するより保険を活用した方が料金は安い印象だろう。しかし、保険で医薬品を受け取るには必ず医師の診察を受け、処方箋を書いてもらい、薬局に足を運ばねばならない。このようなステップと、市販で購入するものを金額だけで比較するのは難しい。OTC医薬品の価格が医療保険の自己負担に収まれば、セルフメディケーションを推進しやすく、そのような数字的アプローチも考えられる。一方で、医療保険は自助で対応できない病気をしっかり支えるという視点も重要であり、その点を国民に理解してもらう必要がある。
保湿剤を美容目的で使用するといった誤った用途は指摘しやすいが、保険給付範囲そのものの見直しについては、丁寧な議論が求められる。ただ、保険財政の厳しい状況を踏まえれば、当然、検討すべきだと考える。
─次回改定に向けた課題について。
今回は介護や障害福祉との同時報酬改定で、さらに、新たな医療計画、医療費適正化計画などをはじめとする一連の計画がスタートする時期とも重なった。一方、令和8年度は団塊の世代がすべて後期高齢者に移行する「2025年」の次の年となる。高齢者がボリュームゾーンにいることに加え、新しい地域医療構想の議論が進んできていることも予想される。
また、かかりつけ医機能報告の運用が始まっており、「かかりつけ医」もしくは「かかりつけ医機能」の実態がある程度は浮かび上がってくるだろうと考えている。
医療DXも引き続き重要な要素になる。オンライン資格確認等システムだけでなく、電子処方箋管理サービスや電子カルテ情報共有サービスが運用され、医療にどのような変化が生じるかを頭に置きながら議論をしていくことになると認識している。
─健保組合に向けたメッセージについて。
健保組合専用イントラネットに「診療報酬改定コーナー」を設けており、4月5日付で、令和6年度診療報酬改定について厚労省の担当者が説明している動画を掲載している。
こうした取り組みのほか、今回をはじめとするインタビュー取材については、一般紙、専門誌を問わず基本的にすべて受けているので、多くの皆さんが少しでも医療に興味を持ち、自身もしくは家族が受ける医療を理解したうえで医療機関を受診いただきたい。
このような知識を持っていて決して損はないはずなので、人ごととは思わず、ぜひ自分ごととしていただきたいし、われわれはできるだけわかりやすく伝える努力を続けたい。