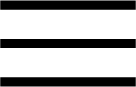健保ニュース
健保ニュース 2024年5月下旬号
市場拡大再算定の対応
松本理事 新薬収載機会を最大限活用
中央社会保険医療協議会(小塩隆士会長)は15日、総会を開催し、新規医薬品18成分22品目を5月22日付で薬価収載することを承認した。
このうち、①トルカプ錠②エルレフィオ皮下注③ビロイ点滴静注用─が費用対効果評価の対象(H1)に該当した。
また、原価計算方式で算定されたビキセオス配合静注用は「有用性加算Ⅰ(45%)」と「市場性加算Ⅰ(10%)」、アキュミン静注は「有用性加算Ⅱ(5%)」、アミヴィッド静注は「有用性加算Ⅱ(10%)」、ビザミル静注は「有用性加算Ⅱ(5%)」、オビザー静注用は「有用性加算Ⅱ(10%)」と「市場性加算Ⅰ(10%)」、シスタドロップス点眼液0.38%は「有用性加算Ⅱ(15%)」と「市場性加算Ⅰ(10%)」、サルグマリン吸入用は「画期性加算A(75%)」と「市場性加算Ⅰ(15%)」の対象となったが、このうち、ビキセオス配合静注用とサルグマリン吸入用は製造原価の開示度が50%未満のため、補正加算を乗じずに薬価を算定した。
令和4年度薬価制度改革は、薬価の透明性を確保する観点から、原価計算方式における製造原価の開示度向上をめざし、開示度50%未満の場合の加算係数を「0.2」から「0」へと厳格化。いわゆる「ブラックボックス」から「ホワイトボックス」への転換を図った。
また、この日の総会では、厚生労働省が新医薬品の承認時期の取り扱いについて、薬事審議会の開催から3週間以内を目処に承認すると整理したことに伴い、「年7回の薬事承認を予定している」と説明。
薬事承認の回数増加に伴い、薬価収載の頻度についても現状の4回から7回に増加させ、より迅速な薬事承認および薬価収載の手続きを実施していく方針を示した。令和7年度からの対応となる見通しと報告した。
健保連の松本真人理事は、薬価収載の回数が年7回となることを受け、「患者が従来よりも早く新薬にアクセスできることは望ましいこと」と発言。
「薬価収載のタイミングが早くなれば、患者のみならず企業にとってもより迅速な売り上げにつながるメリットがある」との認識を示した。
他方、市場拡大再算定については、平成28年に大臣合意された「薬価制度の抜本改革に向けた基本方針」で、「一定規模以上の市場拡大に速やかに対応するため、新薬収載の機会を最大限活用して年4回薬価を見直す」こととされたと指摘。この考え方は、「年4回という回数よりも、新薬収載の機会というタイミングを捉えていることに重みがある」と強調した。
このため、令和7年度以降は、市場拡大再算定の回数を最大限増やしていくよう要望。
合わせて、「市場が大幅に拡大した場合、患者負担と保険財政への影響もより早期に緩和する必要がある」との見解を示した。
厚労省は、新薬の収載と関連する対応事項について、「薬価制度全体の運用のなかで今後検討を進めていく」と応答した。