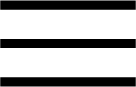健保ニュース
健保ニュース 2023年10月中旬号
医療保険部会が骨太事項を議論
薬剤自己負担見直しに賛否
佐野副会長 給付範囲の見直し検討を
社会保障審議会医療保険部会(田辺国明会長)は9月29日、政府の「骨太方針2023」に記載された「薬剤自己負担の見直し」をテーマに議論した。
委員からは、「薬剤自己負担の見直し」に対して賛否両論の意見があり、厚生労働省は年末の取りまとめを視野に入れ、検討を進めていく意向を示した。
「国民負担の軽減」と「イノベーションの推進」が求められるなか、政府が6月16日に閣議決定した「骨太方針2023」は、「医療保険財政の中でイノベーションを推進するため、長期収載品等の自己負担のあり方の見直し、検討を進める」と明記。
また、「医薬品の迅速・安定供給実現に向けた総合対策に関する有識者検討会」が6月9日に取りまとめた「報告書」は、「新薬の研究開発に注力する環境を整備する観点や、長期収載品の様々な使用実態に応じた評価を行う観点から、選定療養の活用や現行の後発品への置き換え率に応じた薬価上の措置の見直しを含め、適切な対応について、検討すべき」と記載した。
こうした方向性やこれまでの議論を踏まえ厚労省は、この日の会合に、薬剤自己負担の見直しに関する主な項目として、①薬剤定額一部負担②薬剤の種類に応じた自己負担の設定③市販品類似の医薬品の保険給付のあり方の見直し④長期収載品の自己負担のあり方の見直し─の4案を提示。
①は、外来診療や薬剤支給時に薬局窓口等で薬剤に関し定額負担を求める内容で、平成15年4月に廃止された、いわゆる「ワンコイン制」の負担方式を想定する。
②は、医療上の重要性に応じて35%~100%(代替性のない医薬品は0%)の自己負担としているフランスを参考として、有効性など医療上の利益にもとづき薬剤を分類、各カテゴリ別に自己負担割合を設定。
③は、OTC医薬品に類似品がある医療用医薬品について、保険給付範囲からの除外や償還率の変更、定額負担の導入など、保険給付のあり方を見直す。
④は、長期収載品について様々な使用実態に応じた評価を行う観点や後発品との薬価差分を踏まえつつ、自己負担のあり方を見直す対応を提案した。
①と②は平成14年健保法等改正法の附則における7割給付の維持との関係、③と④は医療上の必要性に応じて適切な医薬品を選択できるよう担保する必要性、などを課題に据えた。
健保連の佐野雅宏副会長は、国民皆保険の持続可能性を確保する観点から、「重篤疾患の薬剤を確実に保険でカバーする一方、OTC医薬品で代替可能な薬剤は保険給付範囲からの除外や給付率引き下げなどの適正化により、事業主や被保険者の保険料負担の軽減に繋げるべき」と言及。さらに、長期収載品の自己負担のあり方の見直しについて、「医療費の伸びを抑制して国民負担を軽減することを念頭に、後発品と自己負担を変えることも考えられる」と指摘したうえで、「長期収載品を含めた保険給付範囲の見直しは検討すべき」と強調した。
中村さやか委員(上智大学経済学部教授)は、「経済学的に考えると、②と④が原理原則としては望ましい」と述べ、エビデンスにもとづく議論を要請。また、「自己負担で患者が無駄を減らすのは限定的な面もある」との認識を示し、②の考え方で医学的利益が少ない処方に対しては、その処方を行った医師への診療報酬引き下げも考えていく必要があるとした。
一方、猪口雄二委員(日本医師会副会長)は、「4案とも患者の自己負担が増えることに変わりはない」と指摘したうえで、「国民にとって必要な医療が確保されているのかという観点から、相当に精緻な議論が今後必要になる」との考えを示した。
村上陽子委員(日本労働組合総連合会副事務局長)は、患者負担の増加で経済力がない者が医療にアクセスできなくなり、結果として重症化に繋がることがないよう慎重な検討を要望。厚労省が提案した4項目は、「いずれも医療アクセスの観点から問題がある」と主張した。