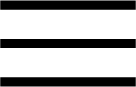健保ニュース
健保ニュース 2022年12月上旬号
高齢者医療制度への支援金等見直し
後期は年820億円の負担増
佐野副会長 改革全体の影響明示を
厚生労働省は11月17日に開催された社会保障審議会医療保険部会(田辺国昭部会長)に、次期医療保険制度改革に向けた後期高齢者の保険料賦課限度額と高齢者医療制度への支援金の見直しを提示した。
後期高齢者医療制度の医療給付費は高齢世代が約1割、現役世代が約4割、公費が約5割を負担することとされ、高齢世代の負担割合は高齢者負担率により定められている。
現行の高齢者負担率の設定方法は、現役世代の減少のみに着目しているため、制度創設時の平成20年度と比較し、現役世代1人当たり後期高齢者支援金の負担は1.7倍と後期高齢者1人当たり保険料の1.2倍よりも大きく増加。
2025年までに団塊の世代が後期高齢者となるなか、当面その傾向が続く一方、長期的には高齢者人口の減少局面でも高齢者負担率が上昇し続けてしまう構造となっている。
このため、厚生労働省は、第1号・2号被保険者の人口比に応じて負担割合の見直しを行っている介護保険を参考に、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じとなるよう、高齢者負担率の設定方法を見直す。合わせて、高齢者世代内で能力に応じた負担を強化する観点から、後期高齢者の保険料負担のあり方を改めることとした。
令和6年度から後期高齢者の保険料賦課限度額を現行の年額66万円から80万円へ14万円引き上げるとともに、年金収入のみで153万円を超える後期高齢者の保険料を所得に応じ引き上げ。被保険者全体の約4割が保険料引き上げの対象となる。
低所得者層の保険料負担が増加しないよう、現在、1対1となっている保険料の均等割と所得割の比率について、年金収入のみで153万円を超える後期高齢者を対象に所得割の比率を引き上げる。
保険料賦課限度額と高齢者医療制度への支援金を見直す影響により、後期高齢者医療制度における6年度の保険料負担は年額820億円、加入者1人当たりで4000円(月額340円)それぞれ上昇。
これに対し、現役世代の健保組合は同290億円、同1000円(同90円)それぞれ保険料負担が軽減する。また、▽協会けんぽは年額300億円減、加入者1人当たり800円(月額70円)減▽共済組合等は同100億円減、同1100円(同90円)減▽国民健康保険は同80億円減、同300円(同20円)減─に保険料負担を抑制。
後期高齢者の保険料について、負担能力に応じた負担へ見直し、給付と負担のバランスや現役世代の負担上昇の抑制を図る。
このほか、次期医療保険制度改革では、6年度から後期高齢者医療制度が出産育児一時金にかかる費用の7%を負担する仕組みを導入する方向性が検討されており、後期高齢者の保険料負担はさらなる増大が見込まれる。
他方、被用者保険者支援のあり方や前期高齢者給付費の報酬水準に応じた調整など、厚労省が10月28日の医療保険部会で提案した「被用者保険者間の格差是正の方策」は、この日の会合で見直しの方向性が示されなかった。
健保連の佐野雅宏副会長は、今回の医療保険制度改革による財政影響を含む全体像を明示するよう要望したうえで、「今回の改革は、現役世代の負担軽減につなげることが最大の目的であり、世代間・世代内の負担バランスや負担能力に応じた見直しも合わせて行うべき」との考えを改めて示した。
高齢者の保険料賦課限度額や高齢者医療制度への支援金のあり方について、後期高齢者1人当たり保険料と現役世代1人当たり後期高齢者支援金の伸び率が同じになるよう、高齢者負担率の設定方法を見直すことは、今回の改革の趣旨に合うと指摘し、実現を強く求めた。
他方、「被用者保険者間の格差是正の方策は、あくまでも現役世代間における見直しであり、当然ながら現役世代の負担軽減を前提とするなかでの調整に留めるべき」と言及したうえで、「仮に前期高齢者給付費の調整を行うとしても、報酬水準に応じた調整を行う部分は極力小さくするのは当然」と強調。
健保組合に対する支援策を充実・強化し、少なくとも全体として健保組合の負担軽減につながる形の内容にしないと、健保組合、事業主、加入者の納得は決して得られないと訴えた。