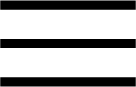健保ニュース
健保ニュース 2020年10月中旬号
医薬品の保険給付範囲の見直し
保湿剤、花粉症薬を検討例に
毎年薬価改定 調整幅のあり方も提言
財務省は9日に開催された財政制度等審議会の財政制度分科会に薬剤費の適正化に向けた医薬品の保険給付範囲の見直しや、毎年薬価改定における調整幅のあり方などを提案した。
初めに、薬剤費が大きく増加する背景となっている新規医薬品を保険収載する場合は、保険収載と既存医薬品の保険給付範囲の見直しを財政中立で行うことも含め、「医薬品に対する予算統制のあり方を抜本的に見直すべき」と問題提起。
そのうえで、新規医薬品の薬価算定は、薬価算定組織の審議経過の公開が不十分と指摘し、薬価算定プロセスの透明性を向上させ、根拠の明確化を図るべきと強調した。
具体的には、国民負担の増大を抑止するため、開示が不十分なうえに高い営業利益率が上乗せされている原価計算方式の見直しに取り組むべきとした。
一方、既存医薬品の保険給付範囲の見直しは、除外と縮小の2つの手法があると指摘。
保険給付範囲からの除外の場合、保険適用外の医薬品にかかる薬剤料だけでなく、初診料などの技術料も含めて全額自己負担となりかねないことから、技術料は保険適用のまま医薬品だけ全額自己負担とする保険外併用療養費制度の新たな類型を設ける対応が必要と訴えた。
今後の検討例として、健保連が平成29年9月14日と令和元年8月23日にそれぞれ公表した「政策立案に資するレセプト分析に関する調査研究Ⅲ、Ⅳ」で政策提言した「保湿剤(他の外皮用薬等との同時処方がない場合)」と「花粉症治療薬(OTC類似薬を1分類のみ投薬する場合)」が示された。
保険給付範囲の縮小の場合は、フランスにおける薬剤の種類(有効性)に応じた患者負担割合の設定や、スウェーデンにおける薬剤費の一定額までの全額患者負担など、諸外国の手法を幅広く検討すべきとした。
令和3年度の毎年薬価改定については、国民負担の抑制を最大限実現する観点から、薬価と市場実勢価格の「乖離率」でなく、「乖離額」に着目して対象範囲を決定すべきと主張。また、全品改定を視野に、薬価の水準が高く乖離率が相対的に小さくなる先発医薬品も幅広く対象品目に含めることを要求した。
さらに、市場実勢価格の過重平均値に対して2%を上乗せしている調整幅は、流通安定のための最小限必要な調整比率とされているが、「平成12年から約20年間、2%の水準が見直されていない」ことを問題視し、合理的な根拠も含め、調整幅のあり方を見直す必要があるとした。
調整幅については、昨年11月8日の中央社会保険医療協議会・薬価専門部会で支払側委員から2%の水準の妥当性について検討を求める指摘があった。この日の財政制度分科会に出席した委員からは、「国民負担を軽減する余地があるのではないか」等の意見があがったという。
他方で、毎年薬価調査・改定の実現を機に、医薬品の価格を巡る公的統計の改善を図り、薬価調査を待たずとも市場実勢価格の大まかな動向を「見える化」する対応も求めた。
フォーミュラリのGLに後発品の選定基準を設定
後発医薬品のさらなる使用促進に向けては、今年9月までの使用割合80%の目標に対し、「達成の可能性が高い」と見通したうえで、後発品の使用割合は地域や保険者ごとに差が大きいことを踏まえつつ、さらに促進するための目標を設定すべきと要望した。
その際は、薬価が高額なバイオ医薬品について後続品(バイオシミラー)への使用を促すための新たな数量目標の設定や、保険者別に公表している後発品の使用割合を医療機関別にまで拡大することが必要と指摘。
さらに、医学的妥当性や経済性を踏まえた医薬品の使用方針とされる「フォーミュラリ(推奨医薬品リスト)」のガイドライン策定に国が取り組むなかで、後発品の選定基準を設けることなどを検討するよう提言した。
また、約6割の薬局が算定している「後発医薬品調剤体制加算」は、後発品の80%シェア達成に合わせ、加算のあり方について見直しを行うべきとした。
不妊治療の保険適用を実現
保険外併用制度を柔軟活用
子ども・子育て分野では、「不妊治療への保険適用を実現し、安心して子どもを生み育てられる環境をつくる」とした菅内閣の「基本方針(9月16日閣議決定)」に沿って、不妊治療への保険適用の実現に向けた取り組みを進めていく必要があると提言した。
保険適用の実現は、現行の保険外診療への助成に比べ、▽経済的負担の軽減につながる▽一律な給付内容が保障され、治療内容の標準化・費用の明確化が図られる▽立替払もなく保険証のみで手続きが完結する─などのメリットがあると指摘。
一部の高度な不妊治療へのニーズに対応し、保険外併用療養費制度の柔軟な活用も検討すべきとした。
このほか、少子化対策は、賦課方式をとる日本の社会保険制度の持続性の確保や将来の給付水準の向上につながるものであることを踏まえると、「医療保険制度を含め、保険料財源による少子化対策への拠出を拡充するという考え方も検討する余地があるのではないか」と問題提起。
少子化対策の安定財源確保のあり方については、税財源の検討のみならず、保険料財源も含め幅広く検討を行っていくことを求めた。